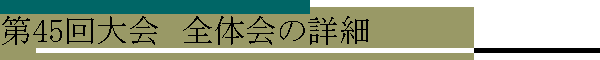
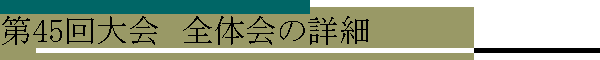
社会主義圏の崩壊を契機に、米ソを主軸にした東西冷戦体制は、世界規模の国際秩序としては「終結」した。だが、「熱戦」をもともなう歴史過程によって形成された東アジアの分断は、グローバル化の進行する今日においてもなお強固なかたちで継続しており、いまだに朝鮮戦争の「停戦」状態から抜け出すことすらできないでいる。二〇〇八年は、朝鮮半島の南北両政府が「建国」「創建」を宣言して六〇年目にあたり、それぞれで大きな記念行事が開催された。六〇年といえば、干支でいえば一回り、およそ二世代の時間が経過し、人口的にも「分断後」世代が大半を占めるようになっている。それにともない、北と南に別々の「国」があるということは既成事実となり、東アジアの現代に生きるわたしたちの思想と行動を束縛するとともに、さまざまな葛藤を生み出している。
だが、六〇年前をふりかえったとき、その時代を生きていた人のなかで、誰がこれほど長期に分断が存続すると予測し得ただろうか。本大会では、その分断の「起源」ともいえる一九四八年前後の時代に遡行し、再編される植民地主義と東アジアにおける冷戦体制の形成によって、熱気と混乱に満ちた「解放」の空間が、時に激しい暴力をもともなって分断、硬直化していくプロセスを歴史学的にとらえなおす。それは同時に、分断を所与のものとしていてはみえてこない、歴史の不確定性、流動性、さらには可能性を再発見することでもある。
朝鮮史研究会の大会としては、一九九五年に「「解放」五〇年―朝鮮の分断と統一」と題して、現代史を中心とした統一テーマを組んだことがある。それから十数年が経過しているが、その間、韓国や日本などで現代史研究が著しく進展している。また、韓国の「過去清算」事業でも、長らくタブーとなってきた解放直後の時代の諸事件についての真相究明が進んでいる。それとともに、そうした流れへの反発として「ニューライト」のような動きが登場していることも事実であり、議論がまきおこっている領域でもある。本大会は、そうした研究と議論の蓄積をふまえながら、そこに一石を投ずるものである。
いかなる事象も、それが何らかのかたちで「帰結」するまでのあいだに、いやほぼ動かしがたい「現実」となってからも、オルタナティブな試みや多様な葛藤がダイナミックに展開する。それは、「結果的」に「大勢」としては、否認されたり、排除されたり、鎮圧されたり、忘却されたりするものであっても、その歴史的経験を結果論としてのみ総括するならば、それは「勝ち組」の歴史叙述にしかならない。それに対し、本大会の各報告は、どう「帰結」するかは不確定の状態で揺れ動くプロセス、そこで繰り広げられる変革のための運動、その時空間を生きる人々の経験、そのなかで発せられる言葉に鋭く切り込もうとする点に、共通する特色がある。それは、たとえば一九四五年八月一五日を迎えても「解放」されなかったものは何か、三八度線以外にどのような「分断」が形成されていったのか、といったことを問い直すことにもつながる。また、「韓国では…」「日本では…」といった単位で閉じた叙述をただ並べることによってではなく、境界をこえ東アジア規模で形成される関係性を歴史的にとらえていこうとする点にも、本大会の特徴がある。不確定性に満ちた朝鮮現代史を歴史学的に再検証することは、朝鮮半島のみならず東アジアの現在と未来を考えるうえでも、必要不可欠な想像力を提供してくれることであろう。
分断状況は朝鮮史研究を規定している。その意味では、現代史を専門にしていない研究者にとっても深く関係のあるテーマといえる。積極的な参加を期待したい。
(文責・板垣竜太)
![]()
米軍政・大韓民国政府の下で死亡者数三万人内外といわれる大規模な虐殺が発生した済州四・三事件は、周知のように、八〇年代後半の韓国民主化運動の高揚とともに、真相究明・過去清算の要求が噴出し、これまで四・三事件全体の展開過程と被害実態の究明に多くの努力が払われてきた。当時、韓国で本格化し始めた解放前後史研究において、「四・三事件=共産主義暴動」という公的言説を否定し、四・三事件は済州島民衆による抗争であったという観点からの研究が重要な位置を占めるようになった。それらの研究により、済州島民が抗争に参加した背景・要因として、済州島民の抵抗の歴史、指導勢力の抗日運動経歴、当時の済州島の社会経済状況などが分析され、外部勢力とは関係のない済州島民の自律的な闘争であったことが示された。
しかし、一九四八年四月三日の蜂起から六〇年目を迎えた今年、済州、ソウル、日本で開催された各シンポジウムでは、四・三事件の歴史的位置づけをめぐって再び論争が展開された。このことは、九〇年代後半以降の真相究明運動の社会的要求と政治的局面のなかで、国家権力による虐殺という真実の解明および「犠牲者認定」がまず優先され、四・三事件の性格や歴史的な評価、とりわけ抗争という側面について議論が留保されてきたことが背景にあるが、より根本的には、済州島民衆の運動に対するさらなる実証的研究と観点についての議論が必要であることを示唆している。従来の済州島民の抵抗に関する記述は、様々な制約もあり、主に済州島内の運動に対する分析に限られ、済州島という地域的特性に強調が置かれてきた。これまでの真相究明を真に強化し深化させるためにも、「解放」直後の朝鮮の文脈のなかで済州島民衆の運動を捉え、その歴史的意味を問い直すことが必要であると思われる。
このような問題意識から、本報告では、先行研究を検討しながら、あらためて済州島民が置かれていた客観的状況を把握し、済州島の民衆がなぜ運動に参加し、参加した人びとが求めていたものは何だったのかに注目したい。具体的には一九四七年三・一節の発砲事件に対する総罷業・抗議示威に端を発し、翌年四月三日の一斉蜂起と国連監視下の南朝鮮単独選挙を破綻させた後も継続した済州島民の運動の実態をあとづける。済州島の運動それ自体は地域的なものだったが、それを通して「解放」から「分断」へと至る過程のなかに内在した可能性や矛盾、それらが朝鮮民衆にとってはどのような問題であったのかを問うための一助としたい。
![]()
本報告は、大韓民国建国初期において支配体制の構築を中心的に担った勢力であるいわゆる「族青系」勢力の性格を、とりわけファシズムという歴史的現象の継承という観点から明らかにすることによって、李承晩政権の一般的なイメージである「親米買弁政権」という像とはかなり異なる姿を史料を通して描き出すとともに、その歴史的淵源を検討することを目的とするものである。李承晩政権についての既存の研究においては個人の独裁という印象が強いため李承晩という個人に関心が集中する傾向が顕著であるが、これを一つの政治体制として把握するためには独裁者というスペクタクルに惑わされることなくその独裁者を実際に支えている勢力の実態を把握する作業がまず必要だろう。その意味で本報告は李承晩政権を立体的に捉えるための基礎作業であるとも言える。
またこの作業は南北分断体制の歴史的形成過程を探求するものでもある。一般的には米ソ分割占領の下で形成された分断体制を北は社会主義、南は資本主義といった非歴史的類型論で整理することに満足しているうらみがあるが、北の体制がすぐさま社会主義体制へと移行したわけではないのと同様に、南においても資本主義に対して距離を置きむしろこれを統制しようとする主張が初期には主であって、これが清算されていく具体的な歴史過程が存在していたことに注目する必要がある。朝鮮戦争を通して東西陣営にそれぞれ組み込まれ、五〇年代半ば以降冷戦が経済戦という様相を呈するなかで社会主義あるいは資本主義による経済発展という近代化論的な視角が支配的になる以前には、南北双方において(とりわけ南において)最も基底的なイデオロギーは民族主義であり、そこには他の新生独立国家と同様に第三世界主義的な傾きがみられた。「族青系」のイデオロギーであるといえる一民主義はまさにそのような傾向を帯びた理念であったが、朝鮮戦争の停戦とともになされた支配ブロックからの「族青系」のパージはこのような民族主義を取り除き「自由陣営」という<帝国>への編入を確実なものとするものであった。
ファシズムという観点を敢えて採る理由はまさにこういった歴史性に関わっている。自由主義的で個人主義的な資本主義体制を批判しつつ共産主義に対抗する新たな政治体制、政治理論として登場したファシズムは第二次世界大戦の終結とともに消え去ったのではなく反共を掲げて建国された大韓民国において継承されたのである。中国国民党を通してファシズムを学んだ李範?、転向した元社会主義者梁又正、二〇年代のドイツで哲学を学びナチスズムの影響を受けた安浩相らを中心として生み出された一民主義という全体主義的かつ人種主義的な民族主義こそが共産主義に対抗する理論的支柱であったのであり、当時直接「族青系」と関わりのない一般の政治学者などのあいだにおいても全体主義やファシズムは一概に否定すべきものとして扱われてはいなかった。
しかしこれは冷戦秩序の一方の中心でありかつ朝鮮戦争において国連軍の派兵を正当化しなければならない米国にとっては極めて厄介なものであった。そのため駐韓米大使館は「族青系」を「国家社会主義者」、「人種主義者」として本国に報告するとともに李承晩に対して李範?への不信感を植え付けるなどの工作を行い、ついには「族青系」は権力の中枢部から除去されることとなる。
![]()
発表者はかつて、論文「解放後の金史良覚書」(2001)で、解放直前から朝鮮戦争中に行方不明になるまでの金史良の後半生をたどったことがある。それは、金史良という個人の歴史の探索であると同時に、解放後、北部朝鮮地域での文学状況の探索でもあった。
さらにその後、モスクワのロシア国立中央図書館ヒムキ分館所蔵の『朝鮮新聞』を調査する機会を得、上記論文執筆時には知ることのできなかった金史良のコント「うすらとんまな子供」(同紙、46年3月1日号)などの作品の存在を確認することができた。そしてこのときの調査などをもとに、2004年度の朝鮮学会で、「初期北朝鮮文壇形成史研究(Ⅰ)-『朝鮮新聞』を中心に-」を発表した。
解放後、ソ連軍政下の北朝鮮、および48年9月建国以降の朝鮮民主主義人民共和国の初期の文学は、政治の動きと密接な連関がある。しかしその一方で、この時期は、各分野で近年相当程度に研究が進んできているものの、いまだ不明な点も少なくなく、それは文学に関しても例外ではない。当該地域の政治体制の閉鎖性と政治的変動によるところから、当時どのような新聞、雑誌等が発行され、どのような作品集が刊行されたのか、といった基本的な調査自体が容易ではなく、いまだその全体像は明らかになっていない。同時期の資料は世界各地に散在しており、そのことが、研究をいっそう困難にしていることは確かだが、これはまた、この地域が経てきた歴史的受難・困難をも物語っていよう。
上記の『朝鮮新聞』は、1946年6月30日に創刊され、1949年の終わり頃まで発行されたと思われる日刊新聞である。発行時期が北部朝鮮での最初期に該当すること、文学および文化動向を詳しく伝えているという点で、他にない特徴があり、初期の北部朝鮮の文学状況を知るのに不可欠で、重要な一次資料である。完全な形では、創刊号から49年1月30日発行の第862号まで、スクラップ記事では、49年11月26日まで発行されていたことが確認できる。
本発表では、この『朝鮮新聞』などを中心に、これまでの発表に引き続いて、資料に基づいて解放直後の北部朝鮮地域での文学動向を多少なりとも明らかにし、より包括的に、初期の「北朝鮮文壇」の形成過程について探りたく思う。
![]()
報告では、朝連・民青解散問題の検討を中心に、敗戦後日本における在日朝鮮人管理体制の形成過程について明らかにしたい。一九四五年から四九年までの時期は、朝鮮人団体との対抗のなかで日本政府が戦後日本の在日朝鮮人「管理」体制を作り上げていく、形成期としての意味を持っている。この過程と歴史的意味を明らかにするのが報告のねらいである。
その際、第一に注目するのは、勅令第百一号並びに団体等規正令による朝鮮人団体規制の実態である。一九四九年九月八日、在日本朝鮮人連盟、在日本朝鮮民主青年同盟の全組織と、在日本大韓民国居留民団宮城県本部、朝鮮建国促進青年同盟塩釜支部に、団体等規正令に基づく解散命令が下された。そもそも団体等規正令の前身たる勅令第百一号は、政党・協会の構成員や目的、財政援助者などを一般に公開し、軍国主義的・侵略的団体については解散させてその物質的基盤を奪うことを目的に制定された、「民主化」のための占領管理法令である。この勅令第百一号(及び団体等規正令)の運用において、朝鮮人団体がいかに位置づけられていたのか、また、朝鮮人団体はこれにいかに対応したのかを明らかにする。
第二に、朝連・民青解散の実態とその影響について明らかにしたい。これまで朝連・民青解散は、その後に続く左翼弾圧の一環として言及されることが多く、朝鮮半島情勢と関連づけられる場合でも政治的側面のみが注目されてきた。ここでは、朝鮮人の「生活と政治」の全領域をカバーした朝連の独特の性格に着目し、解散の影響について分析したい。
第三に、以上の分析を踏まえ、朝連・民青解散が、その後の日本の対在日朝鮮人政策において持った意味について検討する。
日韓交渉が始まると、在日朝鮮人をめぐる諸問題について、韓国は「外交問題」として、日本側は「国内問題」として扱うことを主張するが、いずれにしても在日朝鮮人団体と直接協議するという選択肢はなくなっていく。朝連解散問題の歴史的検討は、こうした形成期の特質を明らかにすることにもつながるであろう。
![]()