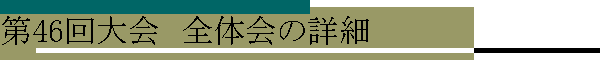
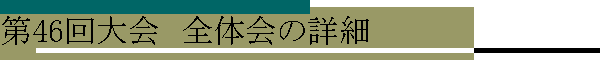
本会は、一九五九年の創立から今年で五〇周年の節目を迎える。これを記念して幹事会では、『朝鮮史研究会会報』の復刻、『朝鮮史研究入門』の刊行、創立の頃から会の運営と朝鮮史研究を担われてきた方々への聞き取りなどの事業を進めている。大会においても「戦後日本の朝鮮史学を振り返る」と題し、主として一九七〇年代までの朝鮮史学について、四人の報告者に論じていただくこととした。
戦前から戦後にかけての朝鮮史研究の流れ、研究方法や問題意識については、既に朝鮮史研究会編『朝鮮史入門』、『新朝鮮史入門』に言及があり、研究者もまた其々の研究および問題意識との関連から論じてきた。戦後の朝鮮史研究に様々な影響を与えたいわゆる「内在的発展論」についても、一九八〇年代から九〇年代にかけて複数の研究者が検討を加えたことは周知の通りである。テーマ設定の目的は、こうした議論にも学びつつ、戦後の朝鮮史学やこれを担った研究者の営為を、研究者の問題意識や研究を支え規定する背景から捉えることにある。背景として具体的に想定されるのは、戦前の朝鮮史研究との研究史的・研究者間のつながり、あるいは研究者を取り巻く現実としての南北朝鮮との関係、これと関連する日本国内の社会情勢の変化、研究者相互の交流や論争などであろう。
大会報告はこうした枠組みの中で、古代史・中近世史・近代史・現代史という四つの報告から構成される。これらの報告から、同時期の研究であっても、研究者の問題意識やその背景には様々な立場のあったことが明らかにされるであろう。その共通点や相違点の意味について考え、これを前提として相互に比較検討することから、各報告が対象とする時代の朝鮮史研究者における各々の課題が浮き彫りになるのではないかと考える。
本年は、大会講演についても右の大会テーマと深く関連するものを企画した。二人の講演者は、朝鮮史研究に果たした会の役割について、経験的な「実感」に基づいてお話をされるものと思われる。企画者としては、こうしたお話をされた講演者、あるいは各報告が対象とする時代や研究者について直接ご存じの方々からの発言により、議論が深まることを期待している。
(文責・大会担当幹事)
![]()
一九四五年の終戦によって、日本を取り巻く状況は劇的に変わったが、それは日本の東洋史学界においても例外ではなかった。とりわけ、朝鮮史学をめぐる状況は、フィールドとしての朝鮮が日本の植民地から解放されたこと、それまで積極的に朝鮮史研究を推進してきた京城帝国大学が研究機関としての機能を喪失したことなどから大きく変化した。こうした状況に加えて朝鮮古代史研究上、軽視できないのは、戦前の日本古代史・朝鮮古代史に大きな影響を与えたであろう、いわゆる皇国史観が否定されたことである。皇国史観が支配的であった戦前の日本においては、『日本書紀』に徹底した史料批判を加えた津田左右吉が攻撃されたことからも明らかなように、『日本書紀』に対する史料批判が制約されていたが、敗戦によってそれが否定され、それによって倭やその史的展開過程に直接的・間接的に影響を与えた高句麗・百済・新羅・伽耶諸国の動向を伝えた『日本書紀』の朝鮮関係記事に対する史料批判の制限もなくなり、斯学の基礎作業である徹底した史料批判・史料考証を経た研究成果の公表が可能となったからである。これによって、戦後、日本の朝鮮古代史研究は新たな道を歩みはじめることになる。こうして出発した戦後日本の朝鮮古代史に関する研究成果は『歴史学研究』や『史学雑誌』の「回顧と展望」に示され、またその研究動向もすでに少なからぬ研究者によって整理されている。
本報告ではそれらの研究成果を参照しつつも、特に戦後日本の朝鮮古代史研究が、当該期の斯界を取り巻く状況と関わってどのように論究されたのか、ということに注視しつつ、終戦後から八〇年代初の日本の朝鮮古代史研究の動向を考究してみたい。それは個々の研究成果に基づいた研究状況の整理に加えて、研究者をして研究に着手せしめた研究者の問題意識を把握することも、当該期の研究を理解し、それをふまえ新たな視点から研究を進める上で必要な作業の一つであると考えたからでもある。具体的には戦前から戦後にかけて日本の朝鮮古代史研究に従事し、多くの業績をあげた末松保和氏や朝鮮古代史研究に大きな影響を与え続けた旗田巍氏の研究や問題意識を、戦後、日本の朝鮮古代史研究上、問題となった大和朝廷の「南鮮支配」や「広開土王碑」をめぐる議論と関連づけながら討究し、それらをふまえ戦後日本の朝鮮古代史研究の特質を探ってみることにしたい。
![]()
戦後日本における朝鮮史研究は、戦前の研究をどのように継承すべきかという問いからはじまった。日鮮同祖論・満鮮一体論・他律性論・停退論などの「ゆがめられた朝鮮史像」を批判・克服し、「新しい朝鮮史像」をつくりだすことを目標として、朝鮮史の主体的発展、内在的発展が追求された。しかし、当然のことではあるが、すべての朝鮮史研究者が同じ方向を向いていたわけではない。右のような動きとは一線を画しつつ、史料に拠って歴史的事実を明らかにしていく実証研究の成果も着実に積み重ねられていった。
報告者に与えられた課題は「戦後日本における朝鮮中近世史研究」を史学史的に考察することであるが、報告者の能力的限界と時間的制約からその課題を網羅的に論じることはできない。本報告では、一九七〇年代までの朝鮮時代史研究に焦点をしぼって、当時の研究が、どのような背景のもとで、何を指向し、どのような成果をあげたのか、その到達点と限界、後世への影響について探ってみることにする。
そのさい、戦前の研究との学問的あるいは人間的つながりを看過することはできない。戦前、朝鮮史研究を日本人が独占した時期、その中心は「京城」であり、京城帝国大学、朝鮮総督府朝鮮史編修会がその研究をリードした。そして戦後しばらくの空白を置いて、朝鮮史研究が再開されるにあたって、その中心となったのも「京城」から引き揚げて来た人々であった。戦後の研究状況を振り返ってみると、七〇年代に入ってからも、戦前の「京城」からの流れをくむ研究者が第一線で活躍しているのである。
この時期を通して、日本の朝鮮時代史研究において質量ともに突出した業績をのこしたのが「京城」出身の田川孝三氏(一九〇九〜一九八八)である。朝鮮時代の社会経済史を中心としてその研究分野は多岐にわたるが、田川氏の業績が今にいたるまで国内外の研究者に多大な影響を与えていることは周知の通りである。田川氏は「京城」に生まれ育ち、京城帝国大学に学び、「京城」で朝鮮史を研究したのち、戦後は東洋文庫を中心に、史料の収集整理、朝鮮時代史の研究、また中央大学・東京大学等で後進の指導にも従事するという稀有な経歴の持ち主でもあった。
本報告では、戦前の研究に対する批判と克服、「新しい朝鮮史像」を追求する様々な動きを横軸とし、田川孝三氏の「京城」時代からの足跡を縦軸として、戦後日本における朝鮮時代史研究をながめたとき、はたして何が見えるのかを考えてみたい。
![]()
戦前歴史学の蓄積を継承すると同時に、その負の側面による制約も受けながら出発した戦後日本の朝鮮史研究は、一九六〇年を前後して新しい転機を迎えることになった。一九五〇年代後半から北朝鮮・韓国で本格化した実証研究を援用しつつ、戦前の研究を停滞論・他律性論として批判する内在的発展論が台頭するに至ったのである。こうした新しい研究方法は、北朝鮮における社会主義改革の進展および対外的な自主路線の闡明、そして韓国における四・一九民主化運動および日韓会談反対運動の展開など、朝鮮半島で起こっていた一連の動きに刺激された結果でもあった。南北朝鮮での研究は、中世から近代へ移行するための動力の存在を立証しようとする、いわゆる資本主義萌芽論が主流を占めていた。日本の研究者たちは、一部の研究で見受けられる実証の不十分さを指摘しながらも、朝鮮史を内在的・発展的に把握しようとする方法論を基本的に高く評価し、また同じ問題意識に基づいて新しい研究に取り組むようになった。
一九七〇〜八〇年代における韓国の高度成長、そしてそれとは対照的な北朝鮮の経済の低迷や個人崇拝の深化は、日本の朝鮮史研究を取り囲む環境にも大きいな変化をもたらした。朝鮮半島の情勢だけでなく国際的な社会主義陣営の昏迷および冷戦の崩壊・変容は、程度の差はあるといえ社会主義を封建制や資本制を克服した代案として意識していた内在的発展論の方法論に対しても、一定の変化を迫るようになったのである。一九八〇年代後半から、内在的発展論を停滞論の裏返しに過ぎない単線的な発展論として批判する研究が相次いで発表された。特に内在的発展論が抱えている近代志向的性格の指摘は、韓国の高度成長を前にして内在的発展論が批判性を失っていた状況に照らしてみれば、的を射た批判だったと言えよう。
そしてそこからまた約二〇年が経った。一九九〇年代以後は、内在的発展論をのりこえるための新しい模索が繰り広げられた。その結果、支配と抵抗という二項対立の構造から脱して植民地経験を捉えなおすための多様な視角が提出されたが、一方で、植民地・戦争をどのように記憶するかをめぐる対立もまた尖鋭になっているのが昨今の現実である。ここで、今日における日本の朝鮮史研究が抱えている課題を確認するために、戦後の朝鮮史研究を強く規定していた内在的発展論の営為を再吟味してみることは、十分有意味なことであろう。
今度の報告では、特に、内在的発展論という研究方法論の真ん中に立ちつづけた梶村秀樹氏の研究を、同じく内在的発展の視角に立ちながらも、「アジア的特質」および「阻止的要因」を重視して「全構造的把握」の必要性を主張していた安秉珆氏の研究と比較検討することによって、内在的発展論に込められていたより複雑かつ多様な側面を明らかにしたい。まず、資本主義萌芽論として矮小化されがちの梶村秀樹氏の内在的発展論の営為を再吟味する作業になるであろう。そしてそれを通して、内在的発展論に対する否定か執着かといった両極端を退けて、真の止揚のための土台を提示したい。また、内在的発展論の再吟味は、必然的に戦前史学に対する評価の問題も触発することになるであろう。内在的発展論に対する否定が、戦前史学の賛美につながってしまういわゆる「朝鮮観の先祖がえり」を警戒しながらも、もう一つの極端である戦前史学の全面否定も避けなければならない。そしてこのような視座は、安秉珆史学の再吟味を通じて得られると期待する。
![]()
戦後日本における朝鮮史研究について旗田巍は、敗戦を契機とする新しい研究はただちには生まれず、「戦後の数年間は、朝鮮史研究は、空白状態」であったという。そしてそれは、ようやく「既成の朝鮮史研究の再建という方向」で打開される一方で、「内外の激動のなかに生まれた民主化の動きにこたえる方向」が次第に生まれ、朝鮮史研究会結成に至ったと語っている。ここであらためて着目したいのは、後者の動向に関し、「朝鮮本国(南北)および在日朝鮮人の新しい朝鮮史への要求が大きく関係していた」(強調引用者)と指摘されていることである(「朝鮮史研究の課題」『朝鮮史入門』一九六六年)。
研究会創立当初における「現代史」とは、植民地期を含み、今日でいう近現代史を貫くものとしてイメージされる部分があった。一九四五年以降しばらくの間は、戦時下はもちろん、関東大震災時の体験でさえも、まさに同時代史であり、「現代史」研究は、八・一五という画期を強く意識し、激変する/旧態依然とした社会との関わりを深く反映しながら、取り組まれ、論じられていったのである。
すなわち「新しい朝鮮史への要求」には、従来重視して取り上げられてきた、戦前来の朝鮮史像の問いなおし・克服という課題とならんで、とりわけ「現代史」については、「新しい朝鮮」像そのものをいかに捉えるか、という課題もが重ねられて追究されていた。冷戦の展開のなかでの旧体制解体の歪み、日本の「過去清算」の不問・朝鮮分断の固定化という情勢に規定されながらも、南北朝鮮においてと同様、在日朝鮮人も新たに自らの歴史を学びなおし、研究を進めるが、それは不可避的に、自らが日本に在るということ、そして、「新しい朝鮮」を、いかなる歴史的経緯のなかに位置づけて認識するのかを、問い・問われながらおこなわれたのであった。
本報告は、このような問題意識から、同時代史としての朝鮮「現代史」研究を、在日朝鮮人による「新しい朝鮮史への要求」を辿りながら振り返ってみたい。時期としては、朝鮮史研究が「沈滞・空白状態」だと捉えられた戦争直後の数年間における、在日朝鮮人による同時代史的取り組み・研究をも含め、日韓条約締結前後期までを中心に取り上げる。
![]()