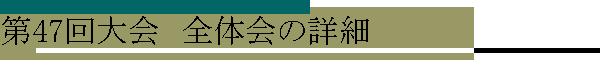
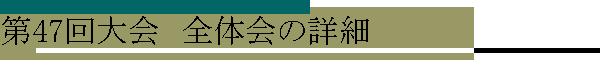
近代日本が行った朝鮮侵略と植民地支配は、日朝関係を大きく歪め、様々な禍根を残した。日本社会は、今なお、戦後補償を始めとする諸課題を未解決のまま抱えている。私たちはこれらの課題にどう向き合っていくのか。この問いは近代の日朝関係における歴史的な過程に根ざしているだけではなく、朝鮮近代史研究への視角やその位置づけとも密接に関わっていよう。特に本年は、「韓国併合」から一〇〇年を経た節目にあたり、各学会における大会テーマや雑誌の特集、日韓の市民運動の場などで「韓国併合」をめぐる議論が積極的になされている。
私たちは右の状況を意識しつつ、本年の大会では、日本による「韓国併合」と植民地支配について、「断絶」と「連続」の視点から考えることにする。もちろん「断絶」と「連続」という視点は、決して新しいものではない。研究史的にみれば、植民地収奪論、植民地近代化論、あるいは植民地近代性論などの議論も、これらの視点に関わるものであった。しかし、これに対して本年の大会で射程に入れようとするのは、植民地朝鮮という事象をめぐる「断絶」と「連続」だけではなく、大韓帝国期から植民地期、植民地期から現代にかけての「断絶」と「連続」であり、さらには植民地認識における「断絶」と「連続」である。なぜならば、「韓国併合」の意味を捉えるには、植民地支配の実態把握のみならず、「解放」/日本敗戦から現在に至るまで、私たちが日本による朝鮮の植民地支配をどのように認識してきたのかという現在の問題をも扱わねばならないと考えるからである。そして、このような議論を通じてこそ、「韓国併合」によって引き起こされた事象が、一〇〇年を経て今もなお私たちに何を問い、どのような解決を求めているのかという問いへの答えも導き出されてくるであろう。
以上のような問題意識のもとに、私たちは康成銀氏、朴俊炯氏、金富子氏、吉澤文寿氏の四人の方々に報告していただくことにした。
康成銀氏は、一九〇五年の韓国保護条約に対する高宗皇帝の裁可問題をめぐって呈された上疏文の検討から、高宗皇帝「協商指示・裁可」説について批判的に報告することで、現在の国際法・朝鮮史研究が内包する問題点に通じる植民地主義の「連続」について論じる。また、近現代国際法のあり方について「強者の法」的側面にとどまらず、植民地支配の責任問題にどのようにかかわることができるのかにまで射程を延ばして論じるが、これは日本の植民地支配責任と植民地主義の問題について改めて課題を提示することにもなろう。
朴俊炯氏は、清国租界を切り口として、不平等条約体制から植民地体制への転換過程において、朝鮮における清国人の地位と彼らへの認識が、どのように「連続」「断絶」しながら推移したのかを実証することを通して、韓国の「自主独立」志向がもった歴史的意味合いや植民地朝鮮における差別の重層化について論じる。さらには、植民地経験を通過したうえでの課題として、現在の韓国における外国人労働者への認識に「連続」する歴史性についても問題を提起する。
金富子氏は、植民地期における初等教育をテーマとして、「併合」によって独立師範学校がなくなるなど、教員養成制度に「断絶」が見られる一方、植民地支配が教育によって作ろうとした人間像からは、現代にもつながる差別や植民地主義の「連続」がうかがわれるという議論を展開する。
吉澤文寿氏は、日韓国交正常化交渉(日韓会談)における在日朝鮮人の法的地位をめぐる交渉について、強制退去問題を中心に考察する。これは、在日朝鮮人の法的地位問題の具体的展開過程の考察を通じて、日韓会談が日本による植民地支配の清算ではなく、むしろ東アジアにおける日本の植民地主義の再編であったことを明らかにするものである。また、現在の日本における植民地主義の「連続」を明らかにしながら、そのことに無関心な日本社会の「断絶」的な状況についても歴史的な課題として言及する。
いずれも近現代における日本と朝鮮の関係の本質に関わる、意義深い報告になると思われる。議場からの活発な議論を期待したい。
(文責:斉藤涼子・酒井裕美)
![]()
冷戦終結後、日本の戦後補償を求める運動が国際的な広がりをもって展開するなかで、一九〇五年韓国保護条約・「韓国併合条約」など旧条約に関する研究が本格的に行われるようになった。研究では、韓国保護条約調印に関する事実究明と法的効力について論じられ、ほぼ「不当・不法(不成立)論」と「不当・合法論」に分かれた。しかし、日本の学界の反応はといえば、一般的に傍観者的な傾向にあるといわざるをえない。そのような学会の雰囲気の中でも韓国保護条約の研究は進み、当初論じられた条約形式の瑕疵問題から、現在は条約強制性の問題へと論点が移っている。なかでも高宗皇帝の「裁可」の有無が焦点となっている。原田環、海野福寿の両氏は、〇五年に日本側史料『韓国特派大使伊藤博文復命書』、韓国側史料『五大臣上疏文』を使い、高宗皇帝が率先して内閣に日本側との「交渉妥協」を指示し、「第二次日韓協約」を「裁可」したと主張した。これに対して、同年に李泰鎮氏と報告者は原田・海野両氏のいわゆる高宗皇帝「協商指示・裁可」説を批判する論考を各々発表した。しかし、その後も原田氏は報告者の批判に対して直接学問的に反論することなく、自説を「補強」する文章をいくつか書いている。
本報告は、以下の二点について考えてみたい。第一点は、原田氏が「補強」した主張をも含めた高宗皇帝「協商指示・裁可」説について改めて批判する。ここでは、原田氏の史料解釈とその淵源となる氏の歴史観について論じる。また、当時の官僚・儒生の上疏文には、現在学界で論じられている保護条約不法の論点がすでにあらわれていることから、不法・合法論の歴史性を考えることができよう。
第二点は、不法・合法論争の課題について問題提起してみたい。もっとも重要な問題は歴史学と国際法学との対話を図ることによって不法・合法論の対立を乗り越えることである。その際、近現代国際法の「強者の法」としての側面だけではなく、国際法システム自体を当該時期の歴史的産物として捉え直し、その変化と発展方向を植民地支配の歴史とも関連づけて「断絶」・「連続」の視点から考えて見ることによって、二〇〇一年ダーバン会議で議論された植民地支配の責任問題について国際法がいかにかかわることができるのかを論じてみたい。次に、日本の朝鮮植民地責任について、とくに現在も継続する植民地主義の問題を考えてみたい。ここでは明治初年以来の日本中心主義的な歴史認識、東アジアにおける冷戦体制、朝鮮半島分断がいかに植民地主義の継続と関わっているのかについて論じてみる。
![]()
「韓国併合」は、租界(=居留地)制度の一つの帰結であると同時に、その撤廃とともに完成されるべきものであった。
「韓国併合」以前の韓国においては、欧米各国の共同租界をはじめ、同じ東アジアの隣国として嘗てから事大交隣関係を維持してきた清国や日本の専管租界まで存在していた。当時租界は、韓国政府の主権が殆ど及ばない「国のなかの国」を成していたため、「韓国併合」後、植民地朝鮮における統治の一元化を図っていた日本は、一九一二年に地方制度の整備が一段落すると、早速租界の撤廃のために清国及び欧米各国との交渉に取り掛かった。ところが、一九一四年、交渉の末にすべての租界の撤廃が告示されたにもかかわらず、特定の人達に限り租界は有効なものとして残された。すなわち、「韓国併合」とともに公布された「統監府令第五二号」により、清国人労働者は、地方長官の許可なしには、従前の租界以外において居住し業務を行うことが禁じられたのである。これにより、租界は「特権」の空間から「隔離」の空間へとその性格が変化する。
このような租界の性格変化は、日清戦争時、敵国民である清国人の保護及び取締りのために、その居住範囲を租界に制限した「勅令第一三七号」と「保護清商規則」、或いは、日本の台湾領有後に清国人の上陸先を四つの港口に限定した「清国人台湾上陸条例」や、一八九九年の改正条約の発効間際に清国人労働者のみを内地雑居の対象から外した「勅令第三五二号」の公布などにその端緒を見出すことができる。そして、こういった法令の公布が、東アジアにおける中華秩序の崩壊や変容といった問題と絡み合っていたことは言うまでもない。
本報告では、清国租界の地位問題をめぐって、韓清・日英・韓英・日清の間で行われた諸交渉過程を主に検討し、清国人と清国租界の地位の変化を追究する。本報告の狙いは次の三点にまとめられる。第一に、清国との関係を清算し各国と対等な地位に立とうとした韓国の「自主独立」への志向が、外国人との「雑居」に対する両面的な態度を生んだことを浮き彫りにする。第二に、韓半島における各国の特権を回収しようとした日本の統治の一元化により、寧ろ重層的な差別構造が日本本土から植民地朝鮮へ移植されたことを明らかにする。また第三には、「韓国併合」一〇〇年を迎える今日、様々な形で日常的に向き合うようになった「外国人」と「雑居」する方法を考えたい。
![]()
本報告のねらいとしては、第一に、宗主国日本と違って義務教育制度を敷かなかった植民地朝鮮において、総督府が朝鮮人初等教育政策を通じて創出しようとした人間像を時期的差異、民族・ジェンダーの差異に注目しながら、教員政策との関連も含めて分析すること、第二に、とくに一九三〇年代以降に着目して、朝鮮人初等教育の「近代性」と「植民地性」との関係を明らかにすること、第三に、以上を通じて植民地教育とは何だったのか、とりわけ植民地教育政策=「同化」政策概念を再検討すること、の三点である。
植民地支配(教育)政策が創出しようとした人間像に関する先行研究としては、まず宮田節子の研究がある。宮田は、日中戦争を契機として展開された皇民化政策がその究極の目標とした「皇国臣民」という人間像とは「皇軍兵士」であり、「皇国臣民」という造語には「朝鮮の特殊性が反映」していると分析した(「皇民化政策の構造」『朝鮮史研究会論文集』二九、一九九一年)。また金晋均・鄭根埴・姜イスは、フーコーの規律権力論を援用して、職業教育や普通学校で「教育された各種の規律は'近代的産業労働'の原理に属して」おり、「近代的主体としての産業型人間と、軍隊や総動員体制に動員しやすい兵士型人間を同時につくろうとした」と分析した(「日帝下の普通学校と規律」金晋均・鄭根植編著『近代主体と植民地規律権力』所収、一九九七年)。
前者は「植民地性」、後者は「近代性」に主眼をおいた分析といえるが、いずれも男性に当てはまるものであり、ジェンダーの差異が明確とは言えない。後者では、日本人との差異も明確ではない。また植民地教育政策は「忠良ナル国民」(第一次・第二次教育令期)、「忠良ナル皇国臣民」(第三次教育令期)の育成を目標としたが、果たしてそれは「同化」=「日本人化」させようとしたものなのか。表層的な言説(政策理念)と実際の政策展開には、乖離があったのではないか。以上をふまえ、報告では植民地教育が求めた人間像を時期的差異、民族・ジェンダーの差異を政策展開を通じて再検討していきたい。
![]()
本報告は近年公開された日韓会談外交文書を検討することにより、日韓国交正常化交渉(日韓会談)における在日朝鮮人の法的地位をめぐる交渉について、強制退去問題を中心に考察するものである。在日朝鮮人の法的地位についての論議はもっぱら「在日韓国人」法的地位委員会で行なわれた。その議題は国籍、在留許可(永住許可および退去強制)、処遇などであった。本報告で退去強制問題に注目するのは、植民地支配を原因として日本に居住することになった在日朝鮮人の永住許可を議論する一方で、それを全否定する退去強制の条件について合わせて検討されたことの意味を問い直すためである。
従来日韓会談は(不十分だった)「植民地支配の清算」あるいは日米韓反共体制の構築という観点から理解されてきた。しかし、近年の史料公開により、とりわけ前者の「植民地支配の清算」という理解について再検討が迫られている。つまり、張博珍氏が指摘するように、日韓会談は「植民地支配の清算」どころか、むしろそれらの課題を埋め込む過程であるというのである(張博珍『植民地関係清算はなぜ実現できなかったか』ノンヒョン(ソウル)、二〇〇九年)。本報告ではこの視点をさらに発展させて、この会談が大日本帝国の形成から継続してきた植民地主義を再編する過程であるという仮説を提示したい。そして、その仮説に沿って、一九六五年に成立した日米韓体制が単なる反共体制ではなく、日本、朝鮮、そして東アジアにおける植民地主義の再構築であったことを実証したい。そして、この理解は、植民地支配によって形成された在日朝鮮人の法的地位問題を追究することによって、いっそう明確にされるであろう。
本報告は日韓会談における「在日韓国人」法的地位交渉の全期間を検討対象とする。同交渉における退去強制問題について、当時の在日朝鮮人が置かれた状況、大韓民国居留民団ら在日朝鮮人団体の運動および主張、さらに「在日韓国人」法的地位協定発効後の退去強制の実例などをふまえて考察する。これらの考察を通じて明らかになった問題について、大日本帝国の民族支配秩序と戦後朝鮮における南北分断、さらに現在の日本と朝鮮を取り巻く植民地主義に関連づけて、その意味を考えていきたい。そして、二一世紀を生き抜く私たちの未来に対して、歴史的課題に向き合うためのヒントを何らかのかたちで提示することができれば幸いである。
![]()