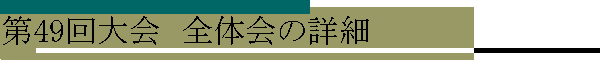
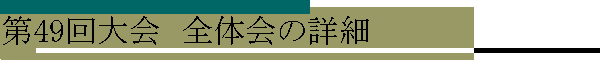
本テーマは、朝鮮王朝と周辺諸国・地域間との「海」を介した交流が、朝鮮王朝にとって、あるいは同時代の東アジア海域交流全体のなかでいかなる意味を持っていたのかという問題を、朝鮮史のみならず、日本史や琉球史の研究者も交えて多角的に検討してみようとするものである。
周知のように、日本の歴史学界では一九八〇年代末ごろから「海域史」が脚光を浴びるようになり、今日まで、前近代の東アジア海域を主要な対象として日本史研究者を中心に多くの成果が積み上げられてきている。しかしこうした流れとは裏腹に、朝鮮史研究においては、日本はもちろん韓国の歴史学界でも、「海域史」はいうにおよばず、より広く海事史全般に対する研究そのものがきわめて不振な状況にある。全体的にみて、朝鮮前近代史に占める「海域史」研究の位置はかなり低いといわざるをえない。
その理由の一つとしてしばしばいわれるのが、朝鮮王朝と「海」とのかかわりの希薄さである。朝鮮時代にはいわゆる海禁と空島化政策のもと、「海」を介した周辺諸国・地域との交流がさほど活発でなく、国家権力も「海」に対する積極的な関心をほとんど持たなかったと理解されている。しかも、そうしたなかで形成された「海」に対する否定的な認識が、今日の歴史学研究の動向をも規定してきたとされる。
しかしながら、朝鮮王朝が「海」とまったく無関係に存在していたわけではもちろんない。限られていたとはいえ、日本との外交関係はもちろん、朝鮮前期においては琉球との関係も「海」を介したものだったし、明清交替期には一時的ながら明との往来も海路によった時期があった。あるいは、朝鮮とその周辺諸国・地域との間の漂流・漂着民をめぐる問題も無視することはできない。朝鮮時代における朝鮮人漁民の漁撈活動や沿岸航路による海上交通なども朝鮮の経済史・社会史における重要な研究テーマであり、それを「海域史」や海事史の文脈から捉えなおす作業は重要な課題といってよい。
近年、韓国ではそのめざましい経済発展とグローバル化の進展を背景に「海洋史」という枠組みで朝鮮前近代史と「海」とのかかわりを捉え直す試みが徐々に活発化してきている。こうした研究状況を踏まえつつ、かつ如上の問題意識を念頭におくとき、日本の朝鮮史研究においても、「海」の視点から朝鮮前近代史を見直し、そこにいかなる問題や課題があり、またいかなる可能性が秘められているのかをあらためて考えてみる必要があろう。
ただし、ひとくちに「海」の視点といっても、上述のようにその接近方法や切り口は様々にありえる。それらすべてを一挙に論じることはとうてい不可能である。よって今回は、手始めに「海域交流」に限定し、従来、朝鮮前近代のなかでもとりわけ「海」とのかかわりが希薄であるとされてきた朝鮮時代に焦点を絞って検討してみることにした。
具体的には、まず総論的にこれまで朝鮮前近代史研究が「海」といかに向き合ってきたかを概観し、問題の所在を確認する。そのうえで、文字どおり海域交流として存在した日本・琉球と朝鮮王朝との交流と、明清交替期に一時期出現した明との「海」を介した交流を取り上げる。そのそれぞれにおける実証的な研究成果によりながら、東アジア海域交流における朝鮮の位相を多様な角度から照射することをめざしたい。
![]()
![]()
本報告は、今回の「朝鮮王朝と海域交流」という統一テーマ設定の意義とねらいを明確にするための、いわば総論としての役割を果たすものである。
「統一テーマのねらい」にもあるように、日本の歴史学界における「海域史」研究の隆盛とは裏腹に、日本はもとより韓国の歴史学界においても朝鮮前近代史研究者の「海」に対する関心は全体的に低く、広く海事史全般にわたって研究は不振といわざるをえない。その理由としてよくいわれるのは、朝鮮王朝が「海」への関心を失い、いわば陸の王朝としての性格を強く有していた(と理解されている)点である。また、「海域史」に限っていえば、そもそも地域論の一環をなす日本の「海域史」の視角そのものへの拒否感が韓国の歴史学界にみられることもその一因として指摘できよう。
とはいえ、朝鮮時代の国家や人々が「海」とまったく無縁に存在しえたわけではないことはいうまでもない。かりに朝鮮王朝が陸の王朝としての性格を有していたとしても、だからといって歴史学研究が「海」を対象から捨象してよいということにはなるまい。現に研究史を振り返れば、不振とはいえ、朝鮮王朝について何らかの形で「海」を研究対象とした成果が皆無なわけではない。前近代史全体に範囲を広げればなおさらそうである。しかも二〇〇〇年代以降、韓国の歴史学界では「海洋史」という枠組みでの研究が俄然活発化し、着実にその存在感を増しつつある。「海域史」とは異なる視角からの「海」を対象とした研究として、こうした動向を無視することはできない。
本報告では、朝鮮前近代史研究がこれまで「海」をいかに取り扱い、「海」といかに向き合ってきたのかを理解するために、まずはそうしたこれまでの研究史を韓国の歴史学界を中心に振り返り、そのおおまかな流れを提示することを第一の目的とする。そのうえで、日本の「海域史」とも対比させながら、近年韓国で活発化しつつある「海洋史」がいかなる問題意識に立脚し、何をめざしているのかについて若干の考察を試みたい。これが本報告の第二の目的である。そして第三の目的としては、そうしたこれまでの研究において朝鮮王朝と「海」との関連がいかに論じられ、理解されてきたかという点をあらためて検討したい。以上を通じて、今回の統一テーマの意義を浮き彫りにできればと考えている。
![]()
中世日朝通交貿易の基本的な特徴として、通交貿易の一方向性と持続性、および通交者の重層性と広域性を指摘できる。前者は、一四世紀末から一六世紀末まで通交貿易が日本から朝鮮へと一方向的なかたちで持続的に展開したことをいう。後者は、朝鮮王朝が倭寇禁圧の実効性を担保するため、日本国王(足利氏)のみならず西日本各地の守護・国人などの領主層を通交者として優遇するとともに、倭寇の構成員や貿易商人をも通交者として待遇したことから生じたものである。
さて、本報告では、中世日朝通交貿易の基本的特徴である一方向性・持続性および重層性・広域性を根本的に検証してみたい。第一に、前者に関しては、そもそも通交貿易はなぜ一方向的に展開したのか、そして倭寇問題を端緒として開始された通交貿易がなぜ倭寇の終息後も持続しえたのかいう問題を、日朝二国間の通交貿易の問題としてだけではなく、東アジア国際環境のなかで考察する。第二に、通交貿易の静態的な観察から析出された重層性・広域性という要素について、これを初期の通交貿易の展開のなかで動態的に考察する。
第一の問題に関しては、明の市舶司廃止にともなう中国海商の日本列島・朝鮮半島への来航途絶、ならびに東アジアと東南アジアとの中継貿易国である琉球の勃興が、中世日朝通交貿易の歴史的前提であることを確認する。そのうえで、高麗・朝鮮の対明朝貢路の海路から陸路への変更、倭寇問題を背景とした朝鮮初期の空島化と海禁にともなう自国民の海外渡航の遮断、琉球の中継貿易を前提とした日本の再中継貿易など、一四世紀後半の東アジア国際環境を背景として、日本から朝鮮への一方向的な通交貿易が展開されたのであり、朝鮮としては合理的な海外物資の調達方法であったことを指摘する。また、南海産物資の琉球からの供給と朝鮮における需要が持続したため、再中継拠点である博多・対馬の貿易商人が商機を恒常的に確保できたこと、それゆえ倭寇終息後に領主層の通交にたいする政治的関心が希薄化するなかで、彼ら貿易商人の経済的欲求こそが通交を持続的に展開させる推進力として作用したことを論じる。
第二の問題に関しては、まず通交者の出現時期を時系列的に整理し、最初期は領主層のみの単層構造であること、一四〇〇年代に倭寇の構成員を包摂する重層構造へと移行し、一四二〇年代以降になって一部の有力貿易商人(博多商人宗金など)を包摂したことを確認する。そのうえで、貿易商人の大部分は、通交者(領主層)から貿易業務を受託するかたちの請負貿易に従事するのが一般的であり、その委託―請負関係の不安定性などを基調として正規の請負貿易から逸脱しようとする志向が潜在的に存在し、それが領主層の没落や通交制度の厳格化などを契機に偽使通交として表出したこと(広域性の実質的縮小)、さらに貿易商人が主体的に関与する偽使通交は対馬宗氏の文引統制の運用により封印されたのであり、一五世紀半ば以降に対馬宗氏が主体的に関与する偽使通交とは区別されるべきものであることを論じる。
![]()
琉球王国は海上交易を基盤に発展した国家である。ゆえに琉球史を「海域史」の典型と見なす発想はごく自然のものかも知れない。しかしながら、琉球史は必ずしも「海域史」のみによって語りうるものではない。王国以前における琉球の交易は、琉球の人々が自ら航海に乗り出して行うというよりも、むしろ外部からの海商の渡来を「待つ」という受け身の形式によって行われたと想定される。琉球王国の登場後その海域交流が活発化する過程においても、琉球の人々全てがその海域交流に携わっていたわけではない。琉球王国の「外部」に存在する人々との連携を含めて、いかなる人々がどのように振る舞うことによって琉球王国の海域交流を支えていたのか、これが琉球史を「海域史」として理解する上での鍵となろう。
本報告においては、朝鮮史における「海域史」の理解に資するべく、琉球王国の海域交流を以下の観点から再検討する。(一)古琉球期、特に一四世紀末から一六世紀にかけての琉球王国の「海域史」を、「久米村」など実際に琉球の海域交流に携わった人々に焦点を当てつつ再検討する。(二)当該時期の琉球―朝鮮関係を通じて、それぞれの国家にとっての海域交流の意義を再検討し、「海域史」を理解する手がかりを模索する。
琉球の海域交流を支えた人々としては、渡来華人の末裔を自認する対外関係の職能集団としての「久米村」人がよく知られているが、その他にも禅僧や海商等多くの人々が渡来してその海域交流に携わっていたことが知られている。この時期の琉球―朝鮮関係についても、主に日朝関係史を中心に多くの先行研究が存在するが、その大多数において日本人商人の介在が想定されており、こうした「担い手」の関与と彼らの意向が両国の海域交流の内実を大きく左右したことは間違いない。
また、この時期の琉球―朝鮮関係には、「偽使」と呼ばれる、少なくとも琉球からの直接の遣使とは異なる使節の往来が多く確認される。この「偽使」を巡る問題についてはその真偽を含めて様々な議論がなされているが、そもそも東南アジアなど他の海域の事例と比較すれば、国家の枠組みに限定して海域交流を理解するという有り様自体、特異というべきかも知れない。本報告ではこのような国家の枠組みをはみだすような存在も含めて、琉球王国がどのように海域とかかわっていたのかを考えてみたい。
![]()
朝鮮王朝は海を通じた諸外国との通交において、外国からの使節団の受け入れが多く、自ら使節団を送り出すことは少なかった。しかし一七世紀の明清交替期(特に一六二一〜一六三六年)においては一時的に朝鮮から明への使節団が、海路を通じて送り出されていた。朝鮮が明に海路使節を派遣していた時期に着目することで朝鮮王朝と海との関わりを知る手がかりになると考えられる。
一七世紀初頭まで明は、『大明会典』にもあるように、朝鮮使節に鴨緑江→遼陽→山海関を通る陸路での入貢を定めていた。ところが一六二一年、後金によって瀋陽と遼陽が陥落する。その結果一六三六年まで朝鮮からの使節団は渤海湾を海路で越えて北京まで往来するようになった。そもそも、海難を恐れた一四世紀の明は高麗に海路で使節を送ることを一三七三年に中断させ、朝鮮建国後の一三九四年からは明指定の陸上貢路(遼東経由)が開通したため、海路による朝明貿易は長期の断絶を経たものであった。朝明間の貿易が海路経由になるとどのような変化が起きたのだろうか。
一六二一〜一六三六年の間の朝鮮からの対明使節を調べると、二七回分は確認でき、そのうち記録(『燕行録』)が残されている使行もある。その記録の中から、貿易に関する情報を中心に分析してみた。
当時の対明使節が用いた船には水軍の船を転用していたものと見られ、朝鮮政府は間に合わせで使臣の船を用意していた可能性が高い。一方で陸上期には行えなかった山東半島の登州からの海路での糧米購入・運搬が行われるようになった。また、陸上での使節派遣に比べ、積載貨物量が増えたことで使節団の人員を増やすなど、朝鮮の海路利用への積極的な対応が見られた。ただ人員が多くなったことで出港地までの沿線の負担や、随員による密輸が増えるなどの弊害も発生した。それに対し朝鮮政府は使節の出港地に荷物検査のための御史を派遣するなど取締を強化した。
明側から見ると朝鮮使節団による貿易の盛行は必ずしも望ましいものではなかった。一六二九年には山東半島の登州から遼東の寧遠を通るルートへ朝貢路が変更され、北京や錦州で荷物検査が行われたり、明将によって朝鮮の使船が拿捕されたりする事件が発生するようになった。
朝鮮は在来の海上交通手段を活用して久しぶりの海路での通交に対応したといえる。しかも政府が積極的に海路の利点を生かそうとしたのであった。外的要因によって海路を用いた外交使節の送り出しが短期間行われた訳であるが、朝鮮王朝は決して海上交流に消極的に対応したのではなかった。
![]()