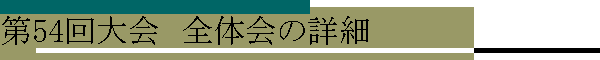
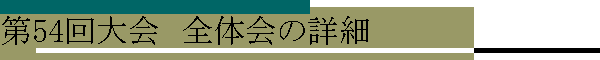
植民地期の朝鮮の歴史は、一般的に日本による支配の暴力性とそれに対抗して近代国家建設を目指す朝鮮独立運動の歴史として把握されてきた。そうした成果を前提に、一九九〇年代以降、近代日本と植民地朝鮮との関係は、支配民族と被支配民族両者における相互作用に立脚した把握へと漸次変化させてきた。これにより、 被支配者側の様々な対応の諸相が明らかにされ、より一層多様な植民地期における社会像・地域像が提起されるようになってきた。
一九九八年、朝鮮史研究会では「朝鮮における地域社会と国家―「公共性」の所在をめぐって」を大会テーマに掲げて、朝鮮近代における地域社会のありようを権力との関係から詳細に実証しつつ、「公共」の所在について議論した。また、朝鮮史研究においては二〇〇〇年代に入り、植民地支配や社会像の特質に迫った「植民地近代」論や「植民地公共性」論の有効性をめぐって議論がなされるようになった。一方、これらに関連する議論として、歴史学全般では、一九九〇年代に「n地域」論といった地域編成における権力の存在を明らかにする地域論が盛んとなった。一九九九年、朝鮮史研究会では、「植民地朝鮮と日本の帝国支配」を大会テーマに「帝国圏」における朝鮮や満洲の位置について検討したが、こうした試みは「帝国」史研究において、日本の「帝国圏」全域を含めた東アジア史像の再検討を問いかける一つの方向性として位置づけられている。
こうした議論を重ねながら、この間、植民地権力と被支配民族両者の相互作用のあり方を踏まえた植民地支配像が模索されてきた。近年もまた、植民地期朝鮮の社会像やその性格をどう捉えるかといった観点から注目され、議論となっている。
本大会では、支配と統合をめぐる理論的な提起や実証研究の進展の現状を、「地域」・「社会」という視点や方法によって、さまざまな立場から実証的に再検討してみたい。改めて基本的な歴史学の所作ともいえる時間と空間の変容を意識して、地域のなかの権力やそこに生きる人びとのありようを明らかにしていくことは、朝鮮植民地支配の特質を考える上で、意味があることであろう。
特に、植民地期においては、都市や農村地帯を対象とする「地域」に関する研究は従来から数多く存在する。
そうした成果を踏まえて、さらに府や道・邑・面などにフィールドを限定することで、より重厚かつ緻密に地域社会のありようを明らかにする報告を、李相旭、崔誠姫、橋本妹里の三氏にお願いした。本大会が、現在における植民地期の朝鮮史研究における地域社会像の実証的な到達点を確認し、地域から見た朝鮮植民地支配の特質を明らかにしていく議論の方向性を見いだし得る場となればと考えている。
なお、理論や研究方法で一つの方向性を求めるのではなく、多様な研究動向が朝鮮植民地支配の特質をどのように明らかにしているのかを、朝鮮史研究の到達点として確認できるような議論になればと考えている。
![]()
![]()
本報告の課題は、3・1独立運動勃発後、改定された「墓地、火葬場、埋葬及火葬取締規則」(以下墓地規則と略)に導入された、制定法上の私設墓地の機制をふまえたうえで、導入前に共同墓地の外部に存在していた諸墳墓と、当該諸墳墓が設置されていた土地との、具体的な関係について、密陽郡墓籍史料を通じて、明らかにすることである。
共同墓地を一方的に押しつける政策を改めた、この墓地規則の改定は、「文化政治」の一環であり、当時、植民地官僚は、これを「大改正」と呼び、大いに慣習を尊重した結果である、としていた。このとき導入された私設墓地の、設置条件の要点は、祭主がそこで墳墓を所有する所の土地の所有者が、祭主自身であることを条件とするという意味で、祭主と土地所有者の同一性にあった。これに対して、報告者は、墓地規則附則第四項墓籍届を用いて、祭主と土地所有者の不一致が多いこと、すなわち、墓地の設置条件をみたせない祭主が相対的に多かったことを示し、「大改正」が、「大いに慣習を尊重したというよりも、土地所有権の有無によって選別したと言ったほうが相対的に適切であること」を指摘した(「植民地朝鮮における墓地規則改定(1919年)について」29頁、『歴史学研究』915号、2014年2月)。さらに、報告者は、祭主と同姓であれ異姓であれ、他人の土地のうえに墳墓が存在しており、それらが興味深い分布の様態を示している点についても、すでに指摘した(「植民地朝鮮における埋葬地(=山林)の所有構造について」、『日本植民地研究』29号、2017年6月)。したがって、本報告では、既に示されている、1919年に導入された私設墓地の歴史性の指摘にとどまらず、導入前の埋葬地の状態の再構成に力を注ぎたい。祭主中心に記述された既発表論文との差異は、土地所有者の観点の導入にある。
主題にある墓地規則附則第四項墓籍届とは、1912年に発布された墓地規則の附則第四項において届出るよう定められた、「本令施行ノ際現ニ存スル共同墓地以外ノ墳墓」の墓籍届である。この墓籍届は、墓地規則施行に伴って、3・1独立運動前に収集されているが、密陽郡の同史料は豊富に残存しており、1919年に制定法上に登場する私設墓地の歴史性を考えるうえで、無視しえない史料である。とりわけ、密陽郡林野関係史料の豊富な残存状態を勘案するとき、同郡墓籍届はその重要性を増す。なお、しばしば混同されるが、墳墓と、墳墓の収容に特化した土地である墓地とは、別の存在である。この区別は、墓地規則においても強く意識されていた。墓地規則の規定する共同墓地の外部に存在していた墳墓の記録を通して、3・1独立運動後導入された私設墓地の歴史性の抽出や、墓地ではない土地について調査が可能であるのは、こうした条件のためでもある。墓地は本報告の対象ではない。林野調査事業を経て主に「林野」へと転化する土地が対象である。
本報告の要点は次の三つである。第一に、祭主による墳墓所有のあり方について、とくに、祭主の位置から土地所有者を分類したうえで、分析する。この分析は、墳墓所有者(祭主)と、墳墓所有者が埋葬地として利用している土地との、具体的な関係について、明らかにする。第二に、墳墓が設置された土地を所有する所有者の、当該土地所有のあり方について、とくに、土地所有者の位置から祭主を分類したうえで、分析する。この分析は、土地所有者と、当該土地に設置されている墳墓との、具体的な関係について、明らかにする。第三に、1919年以降の密陽郡における、私設墓地の利用実態の一部を抽出したうえで、それらが、分析結果から得られる知見に照らして、一定の整合性をもって理解できることを確認し、あわせて、1919年以降、何がどう変化したか、についても確認する。
※上記文では、傍点「・」で強調表示すべき箇所を、技術的理由により下線&太字で表示しております。傍点で正しく表記された文書はこちら(PDF)でご確認下さい。
![]()
本報告は一九二九年一一月三日に勃発した光州学生運動を中心とし、植民地期朝鮮における光州地域の中等教育の検討を課題とする。光州学生運動が起きた一九二九年は第二次朝鮮教育令施行期(一九二二年四月〜一九三八年三月)にあたり、朝鮮の植民地教育が「本格的」に展開した時期といえる。
光州では一九一〇年代から第二次朝鮮教育令施行期にかけて、朝鮮人向けの中等教育機関である光州高等普通学校・光州公立女子高等普通学校・光州農業学校・光州師範学校が設立された。中等教育機関は上級学校への進学資格を得られる学歴形成が可能である一方、最終学歴ともなりえる両面性を持ち、朝鮮人学生の多くにとっては中等教育が最終学歴となった。また、光州は全羅南道の道庁所在地として行政、教育、経済の中心であり、光州周辺の地域には日本人経営の大規模農場が多く、植民地支配と収奪の構造が明確な地域的特色を持っていた。このような中、通学電車の朝鮮人学生と日本人学生との諍いが発端となり、一九二九年に光州学生運動が起こるのである。
光州学生運動は一〇月末から一一月上旬にかけて展開し、総督府が介入する事態となり、多くの学生が負傷し検挙された。先行研究等では「三・一運動と並ぶ事件」と評されている。光州での運動が導火線となり、朝鮮全土及び日本の留学生へも運動が展開したことを考えると、過大評価とはいえないであろう。
先行研究では全羅南道の植民地支配と収奪の構造、中等学生の使命感や抗日意識、一九二〇年代以降頻発する同盟休校や学生組織が運動の背景にあると指摘している。その点については報告者も同意するが、なぜ光州で起きたのか、なぜこのように大規模な運動に発展したのか、その原因を明らかにするには、より詳細に社会的な背景と地域的特色を考察する必要がある。先行研究の成果に加え光州の地域的特色、第二次朝鮮教育令施行期の中等教育、特に光州の中等教育の実態を踏まえたうえでの検討を加えることで、その解明を試みる。
本報告では第一に、光州地域の中等教育の状況を、統計資料等から明らかにする。光州及び全羅南道の教育状況に関する資料は十分とはいえないが、学務局資料・同窓会資料等から分析を行い、光州地域の特色を浮き彫りにする。その作業を通じて運動の当事者である中等学生が植民地期の光州でどのような立場にあったのかを明らかにし、光州学生運動が起こった背景を考察したい。第二に、光州学生運動の実態を明らかにする。この点については上述のとおり先行研究において十分な成果があるが、本報告ではこれに加えて日本での報道、検挙された学生の調書資料等の分析を加え検討を行う。
これらの作業を通じ、主に運動史から研究されてきた光州学生運動に、教育史の視点を加えることで、光州学生運動と光州地域の中等教育の実態を浮き彫りにし、地域からみた朝鮮植民地支配の一事例としたい。
![]()
本報告では韓末から一九二〇年代を中心に漢城府/京城府南山における神社の建立過程について、南山の公園化という視点からアプローチを試みる。従来朝鮮における神社研究では、当然のことながら祭神や祭祀、神輿渡御式など専ら宗教的側面から考察が行われ、神社と朝鮮人との摩擦についてもそのような宗教的要素を通して分析されてきた。本報告では神社を公園として把握することで、日本人地域社会の統合という植民地神社創建の目的を明らかにすると同時に、それが三〇年代に入って朝鮮人に対する同化政策へと利用される教化の機能を創建当初から備えていたことを、南山という地域を事例に日本人による公園形成とそれに対する朝鮮人の反応を通じて提示したい。
本報告ではまず韓末から植民地期にかけて在朝日本人によって建立された神社の多くが眺望の良い景勝地に建てられ境内地が公園を兼ねていたこと、または先に公園を設置した後にその敷地内に神社を建立したことを指摘する。このような神社境内と公園が明確に区分されず、境内と公園とが兼用される様相は日本に固有な公園の特徴であった。前近代まで景勝地として利用された社寺境内を公園へと転換し形成された日本国内の公園の形態が、植民地にそのまま移植されたのである。神社を併設する公園の設置は植民地に「伝統的」風景を創出し、そこに忠魂碑や桜のような日本人としてのアイデンティティを促進する装飾を配置することで、植民地の日本人社会に国民的一体性を創出・維持する教化装置としての役割を果たしたのである。
勿論このような神社と公園を同一視する日本固有の公園観は、当然朝鮮人に受け入れられるものではなかった。韓末南山には日本人居留民有志によって建立された南山大神宮を併設する倭城台公園と、同じく日本人居留民有志によって計画され日韓共同公園として開園した漢陽公園の二つの公園が設置されたが、倭城台公園は韓国併合後、荒廃した南山大神宮の社殿を再建し社号を京城神社と改め規模を拡大すると、その地域社会統合の機能を強化し朝鮮人にまで拡大させていく。朝鮮人にとって倭城台公園は公園として機能しなくなっただけでなく、朝鮮人にも京城神社の氏子として醵出金の支払いや神輿渡御式のような祭祀への参加などの負担が強いられるようになる。一方朝鮮式の東屋が建てられ眺望の良い漢陽公園は朝鮮人からも広く利用されたが、一九一九年朝鮮神宮の建立地に決定する。日本人側から公園に神社を建立することに反対する意見は確認できないが、朝鮮人はこれを「公園の死」であると厳しく評価した。朝鮮神宮が建立された後、公園であった空間は朝鮮人にとって恐れの対象として認識されるようになるのである。
![]()